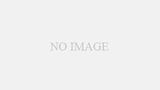「わかったフリ、してしまうんです…」
境界知能の方がよく抱える悩みのひとつに、「本当は理解できていないのに、怒られるのが怖くてわかったフリをしてしまうこと」があります。
これは本人にとって大きなストレスであるだけでなく、周囲の人にとっても「無責任だな」と感じ、関係がギクシャクする原因になります。
本記事では以下を解説します。
境界知能の方が「理解したふり」をやめるための具体的な方法3つ
周囲の人が避けるべき対応3つ
本人・周囲のお互いにとって負担の少ない関係づくりの参考になれば幸いです。
その1 分からないと言う練習をする
「恥ずかしい」「怒られたくない」「迷惑をかけたくない」といった不安から、理解したふりをしてしまうケースは少なくありません。
しかし、本当に怖いのは 分からないまま進んでトラブルになること です。
まずは信頼できる人に対し、
「〇〇の作業内容が途中で分からなくなったので、もう一度説明していただけますか?」
など、言いやすいフレーズを用意しておきましょう。
最初は勇気が必要ですが、繰り返せば自然に言えるようになります。
その2 書いて整理するクセをつける
話を聞いても頭の中で整理できないと、「わかったフリ」につながります。
会話中でもメモを取り、
言われたこと
やるべきこと
不明点
を紙に書き出し、可視化して確認することが有効です。
そのうえで「ここまでメモしましたが、合っていますか?」と尋ねると、自然に確認ができます。
その3 「確認」を日常に取り入れる
例:
「〇〇しておけばよいですか?」
「〇〇は必要ないですよね?」
自分の理解を言葉にして確認するクセをつけましょう。
これは「分かっていないと思われたくない」というプレッシャーを減らし、理解度を高める行動です。
質問は悪いことではなく、成長に必要なこと と自分に言い聞かせましょう。
これは「わかってないと思われたくない」というプレッシャーを減らしながら、自分の理解度も高めていける行動です。
質問は悪いことじゃないし成長するには必要だと自分に言い聞かせましょう。
周りの人がしてはいけないことその1「なんでこんなこともわからないの?」と責める
この一言は当事者に大きなトラウマを与え、「もう二度と聞けない」と感じさせます。
「説明が足りなかったかもしれない」と伝えるなど、相手の安心感につながる対応が望ましいです。
周りの人がしてはいけないことその2 話を一気にまくし立てる・抽象的に話す
境界知能の方は処理できる情報量に限界があります。
「適当にやって」「臨機応変に」など曖昧な指示は混乱の原因になります。
短く・具体的に・一つずつ 伝えることで、相手の負担は大きく減ります。
周りの人がしてはいけないことその3 「自分で考えて」と突き放す
自立を促すつもりでも、相手が「何をどう考えればいいのか」が分からなければ単なる放置になります。
「ここまでは自分で考えて、分からなくなったら聞いてね」と、行動の範囲を具体的に伝えることが必要です。
「少しずつできる範囲を広げる」ことが現実的な支援 です。
自立を促すつもりでも、相手が“何をどう考えればいいのか”がわからない場合、それは単なる放置になります。
まとめ
「わからない」と言えるようになることは、境界知能の方にとって成長への第一歩でしょう。
周囲の人も「察する力」や「正確な理解」を当たり前と思わず、「一緒に確認する」姿勢を持つことで、お互いのストレスが減っていきます。
小さなコミュニケーションの積み重ねが、「理解したふり」からの脱却と、安心できる関係づくりにつながります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。